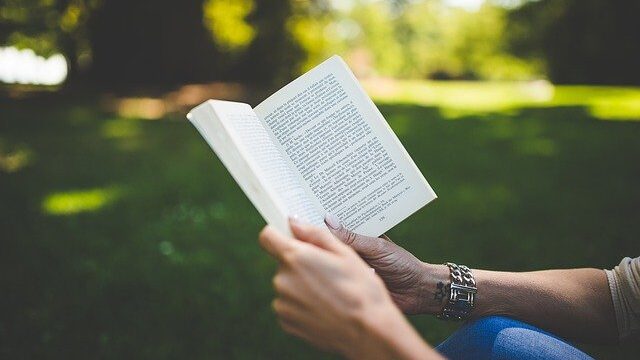地球の人口増加等により、これ以上地球に住むことができず、宇宙に新しい世界を求める。
理由は別にしても、いつかは訪れるかもしれない未来です。
今回読んだのは、新井素子さんの『チグリスとユーフラテス』です!
あまりふだん、SFものって読まないのですが、読書好きの後輩のおすすめで手に取ってみました。
1999年に単行本が出たのですが、いま読んでもなお、考えさせられるテーマを含んでいてとてもおもしろかったです。
ここでは、『チグリスとユーフラテス』のあらすじや感想を紹介していきます。
Contents
『チグリスとユーフラテス』のあらすじ
地球の人口増加や資源問題から、惑星間移民が行われるようになった。
9番目の移民惑星である惑星「ナイン」。
船長キャプテン・リュウイチ、その妻レイディ・アカリを含む30余名の移民船のクルーたちはナインに定着する。
地球を出る際に、大量の人工子宮や凍結受精卵を一緒に移民船に積んでおり、新しい地で新しい社会を築こうとする。
そのかいもあり、一時期、人口120万人を超えるまでに至った。
しかし、人工子宮に問題があったのか、それとも惑星ナインが人間にあっていなかったのか。
原因不明のまま、あるときをピークに出生率が一気に落ちていく。
政府は、なんとか出生率をあげようと、うまれた子どもと家族に手厚い支援を行い、子どもを産む可能性のある”有資格者”は、特別な待遇を受けていた。
しかし、それでも出生率は下げ止まらない。
そして、ついに「最後の子供」ルナが生まれてしまう。
惑星ナインには、ルナと様々な事情でコールドスリープされた人間だけが残った。
ルナには一つの疑問があった。
それは、母親が、自分が最後の子供になると知りながら、なぜ自分を生んだのか。
その答えを知るために、ルナは4人の女を順番にコールドスリープから起こしていく。
いつかは子どもが産まれなくなる恐怖
これって、物語の中のことで済ませられないことなのかなって気はします。
日本もそりゃ、0になるとは今の段階で思えませんが、出生率はがんがん下がってますし、そもそも結婚したくないとか、子どもはいらないって人も多いんですよね。
なぜかって議論はここではしませんが、私の周りだって、子どものいない夫婦も、いても一人っ子って家庭がけっこうある。
それがずー---っと続けば、子どもが減って、産める世代が減って、いつかはってこともあるかもしれません。
小説の中の惑星ナインの場合、人工子宮の問題なのか、新しい土地に人間が適応できなかったのか、どれがってのはわかりません。
でも、これってすごい怖いこと。
世の中おじいちゃんおばあちゃんばっかりになっていくんですよ。
今でもだいぶ人口の偏りはありますし、定年後も働かなくてはいけないなんて、子供の頃は想像もしていませんでした。
現実、70でも80でも働いている人はいますし、そうしなくては全国民が生きていくことはできないって。
子どもがこれから産まれなくなっていくと、いまどころのことではないですよね。
社会が完全に止まる。
その頃にはいろんなことが人間の手を介さなくてもできるかもですけど、どんどん世界が狭くなっていく。
子どもを産むことへの恐怖
『チグリスとユーフラテス』の中では、出生率が下がり続け、子どもを産める遺伝子を持った人間自体が減少。
同世代の子どもの数があっという間に減り、世界で子どもが産まれること自体が、記者会見をするような特別なできごとに。
そうなると、いつかは”最後の子供”が産まれることに。
母親は、自分の子どもが最後に産まれる子どもになってしまうことに恐怖し、子どもを産んでしまったこと自体を喜べなくなる。
そうして、もともと子どもが産まれにくなっているのに、妊娠自体を忌避するようになる。
でも、たしかに自分たちは下の世代がいるうちに死ぬことになるけど、残された子どもが、だれもいない中に一人取り残されるとしたら。
それって恐怖でしかないですよね。
本来、喜ばしいことのはずなのに、それを良いことと素直に思うことができない世界。
だからこそ、『チグリスとユーフラテス』の後半で、産まれ、生きるという意味を考えさせられます。
なぜ人は産まれ、生きていくのか
『チグリスとユーフラテス』では、”最後の子供”であるルナ以外に4人の女性が登場します。
それぞれ、人生で大切にしているものが違う。
マリア・Dは、惑星ナインの後期、出生率が著しく低下したあとも、出生率の高い血筋として特権階級に位置していた。
だから、子どもを産むことが自分の生きている意味だと考えていた。
ダイアナは、惑星ナインが飢饉にみまわれていた時代の管理局の職員。
だから、一人でも多くの人間を生存させることが第一だった。
朋美は、芸術、特に絵を描くことを生きがいとしていた。
人はなんのために産まれてなぜ生きていくのか。
いろんなところで議論になったり、千差万別の答えがあるものです。
本書の中でも、人によってその答えは違う。
中には、生きていることに意味なんてない、と断言する人物もいます。
それでも、私達は生きていく。
それは紛れもない事実で、そこにどんな意味を持たせるのかはやっぱり人それぞれなのかな。
生物学的には、種の保存っていう意味はあるんだろうけど、考えることができる人間の意味をそこだけに置くのはなんか変な気もする。
宗教的には、幸せになることとか、来世によりよく生きるための今世なんて考えもある。
自分なりに、「このことをするために産まれてきた!」と意味づけすることができる人もいる。
私自身は、特に産まれた意味なんてないと思っているけど、どうせ産まれたのなら、楽しく、自分も周囲も幸せでいればいいなと本書を読んで感じました。
おわりに
職場の読書好きの後輩に薦められて読んだ『チグリスとユーフラテス』。
正直、最初は、なかなか古い本だし、見た瞬間、
「うわっ。分厚い!」
なんて思いましたが、今年読んだ中でも特に考えさせられるテーマを含んでいて、読みごたえがありました。
生きる意味ってなかなか考える機会ってないんですよね。
まあいまは自分と家族が幸せに生きることができていればいいのかな。
仕事も割と楽しいし、いい人生を送れているのかも。
その上で、なにかもっと意味づけすることで人生は充実する、とも感じます。