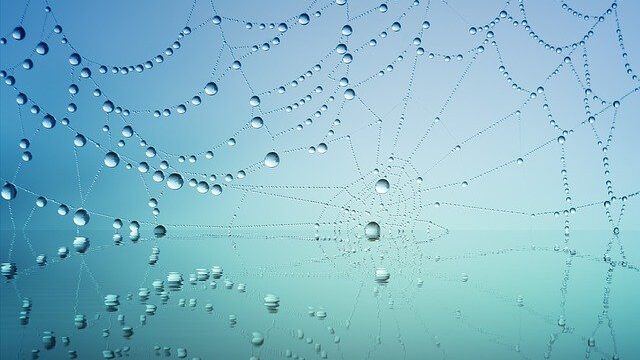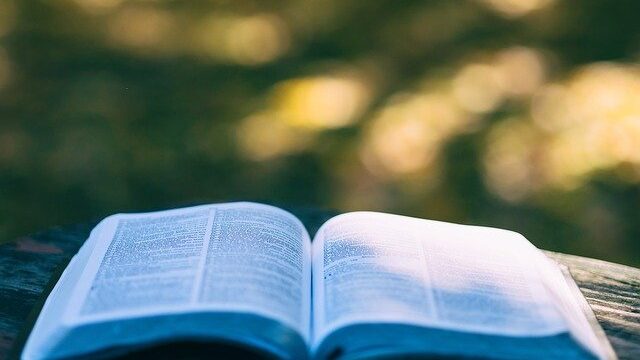日本の著名な作家の一人、芥川龍之介。
誰もが知る彼の代表作と言えば『羅生門』です!
教科書にも載る『羅生門』ですが、これが短い話の割に意外と難しい。
私が初めて読んだときは、
「えっ、これで終わり?」
「何がいいんだろう?」
とよくわからないまま読み終えてしまいました。
当時はまだ高校生でしたしね。
でも大人になって改めて読んでみると、これもまた深い話なんだなと感じさせられます。
ここでは、芥川龍之介の『羅生門』のあらすじや解説をしていきます。
Contents
『羅生門』を読む前に
『羅生門』の時代背景
あらすじに入る前にまずは羅生門がいつの時代の話なのかをしたいと思います。
というのも、いつの話なのかで登場人物の置かれている状況や心情も変わってくるからです。
実際に『羅生門』と同じ出来事が現代社会であったらとんでもないことです。
『羅生門』は平安時代の京都が舞台となります。
羅生門とは、朱雀大路にあった平安京の正門・羅城門のこと。
この当時の京都は、飢饉や辻風(竜巻)、天変地異などで廃れていっていました。
本書の中でも、羅生門はすごくぼろぼろになっていますね。
平安時代といえば、「鳴くよウグイス平安京」なので、794年から始まった平安京を中心とした時代ですね。
その中心である平安京の門がぼろぼろになっているのだから、平安時代の末期、1192年から始まる鎌倉時代にかなり近かったのではないかなと思います。
下人と老婆という二人の登場人物
『羅生門』には、二人しか登場人物がいません。
下人と老婆です。
下人とは、平安時代中期ころに誕生し、明治ころまで用いられた隷属民のことを指します。
平安時代や鎌倉時代であれば、荘園の武士や地頭に隷属して、雑役に従事していました。
召使いがイメージしやすいですが、立場的にはそれよりも悪く、売買の対象にもなっていました。
『羅生門』に出てくる下人は、それまで仕えていた主人から暇を出されて、行く当てもなく、途方にくれて羅生門のかたわらに座り込んでいます。
右のほほにはおおきなにきびがあり、それを気にしています。
にきびがあることから、若者であると推察されています。
老婆は、言葉どおりですね。
年老いたおばあさんのことです。
羅生門の老婆は、背が低く、痩せていて白髪のおばあさんです。
『羅生門』のあらすじ
羅生門と下人
ある日の夕暮れ時、一人の下人が、朱雀大路の羅生門の下で雨宿りしていた。
広い門の下なのに、この男以外に誰もいない。
この2、3年、京都は、地震、辻風(竜巻や台風)、火事、飢饉といった災害が続いていた。
そのため、京都は想像ができぬほどにさびれており、仏像仏具は打ち砕かれて、売り払われていたという。
京都自体がそんな状態なので、羅生門がさびれても修理しようとする者もいない。
荒れ果てたのをいいことに、狐や狸といった動物だけでなく、盗人まで棲みつくようになる。
しまいには、引き取り手のない死体を羅生門に持ってきて棄てていくという習慣ができてしまった。
そんな羅生門だったため、今は下人以外雨宿りをする人もいないのであった。
さて、この下人。
数日前に長年仕えていた主人から暇を出され、行く当てもなく途方に暮れていた。
「どうにもならない事を、どうにかするためには、手段を選んでいる遑(いとま)はない」
このままでは飢え死にするしかないことはわかっており、手段を選んでいる場合ではない。
そのことを肯定するも、その手段……「盗人になるよりほかに仕方がない」ことを積極的に肯定するだけの勇気がでない。
ひとまず、雨風をしのげ、人目につかないところを探して一夜を明かそうと決めて動き出すのであった。
羅生門の上の人影
羅生門の上に続くはしごを見つけた下人は、
「上なら人がいても死人ばかりだ」
と、はしごをのぼり、羅生門の楼の上へと出る。
誰もいるはずがないと高をくくっていた下人であったが、どうも楼の上で、誰かが火をともし動かしている気配がする。
息をひそめて様子をうかがうと、楼の中に転がるたくさんの死体の中に、うずくまっている人間を見つけた。
それは檜皮色の着物を着た、背の低い、痩せた、白髪頭の、猿のような老婆。
この老婆が何をしていたのかというと、老婆は女の死体から髪の毛を一本ずつ抜いているのであった。
最初は恐怖を感じていた下人だったが、しだいに恐怖が消え、この老婆に対するはげしい憎悪が少しずつ動き出すのであった。
先ほどまで、「盗人になるしかない」と考えていた下人が、いまもし、飢え死にか盗人かを選ぶなら迷わず飢え死にを選ぶほどに悪を憎む心が燃え上がっていた。
下人ははしごから上へと飛び上がり、腰の太刀に手を掛けながら、大股で老婆の元へと歩み寄った。
当然老婆は驚き逃げようとするが、すぐに下人に捕まってしまう。
そして下人は、ここで何をしていたのかと問いただすのであった。
下人と老婆
下人に問い詰められた老婆は、両手をふるわせ、肩で息をし、恐怖を感じたまま黙り込んでいた。
下人はその様子を見て、自分の意志がこの老婆の生死を支配しているのだと意識する。
そしてこの意識が先ほどまで燃え上がっていた憎悪の心をいつのまにか冷ましていたのだった。
下人は、安らかな得意と満足を感じながら、優しい口調で再度老婆に何をしていたのかと問いかけた。
すると、か細い声であえぎながら老婆は語った。
「髪を抜いて、かつらにしようと思った」のだと。
下人は、老婆の答えが平凡なことに失望し、それと同時に先ほどまでの憎悪と冷やかな侮蔑が心の中に生まれるのであった。
その気配を感じた老婆は続けて語る。
死体から髪を抜く行為は確かに悪いことかも知れない。
だが、ここにある死体はそのくらいのことをされてもいい人間ばかりだ。
この女もまた、蛇の肉を干し魚だといって売りさばき生活をしていた。
私はこの女のしていたことが悪いことだとは思わない。
そうしなければ飢え死にするからだ。
そうしなければ仕方がないことを知っていた女だから私のすることも大目に見てくれるはずだ、と。
下人は、太刀を収めてこの話を聞いていた。
聞きながら下人の中にある勇気が生まれて来た。
それは羅生門の下では、この男に欠けていた勇気であった。
そして下人は、
「きっと、そうか」
と言ったのちに、老婆の襟髪をつかみながら、噛みつくように言うのであった。
「では、己(おれ)が引剥(ひはぎ)をしようと恨むまいな。己もそうしなければ、餓死をする体なのだ」
言うなり、下人は素早く老婆の着物をはぎ取り、足にしがみつこうとする老婆を、死体の上に蹴りたおした。
そのままあっという間にはしごを折りて夜の庭へとかけていった。
下人の行方は誰も知らない。
『羅生門』の感想・解説
『羅生門』って簡単に言うとこういう話
あらすじを書いてきましたが、すごーくざっくりいうと、
〇どうしようもなくなった下人が盗人になることを決意するまでの物語
となります。
読んだとおり、下人はもう盗人になるしかないと思いながらも、その決断ができずにいました。
それまでは、下人ということなので、人に使われる身ではあるけどまっとうに生きていたことでしょう。
だから、どうしようもなくなってもまだ盗人になる勇気が出なかった。
でも自分以外に悪いことをしている老婆を見たことによって不思議とその勇気が出てくるのです。
あれほど盗人になる決断ができなかったのに、最後は清々しいまでのセリフでしたね。
人間のエゴを表現した作品
『羅生門』は人間のエゴを表現した作品だといわれています。
エゴとは、
「自分の利益を中心に考えて、他人の利益は考えない思考や行動の様式。利己主義」
のことです。
そういう視点で見ると、確かにエゴ満載の小説ですね。
下人は生きるために盗人となる。
老婆は生きるために髪の毛を抜きかつらを作る。
その死体の女性も蛇を干し魚として売っていた。
誰もが自分のことだけを考えて行動しています。
『羅生門』を読んでいると、突き詰めたところ人間の本質はこういう部分なのかという気持ちにもなります。
しかし、登場人物たちの行動が悪い事なのかというと、その状況を考えるとなんともいえないものがあります。
実際に飢えるしかない状況に立てば、自分だって生きるために何をするかはわかったもんじゃない。
人間が人間らしくいられるのは、現代のように衣食住がきちんと守られているからです。
それらがなく、追い詰められれば人間だって獣になります。
エゴというと私の中では悪いイメージを持つ言葉ですが、でも、エゴは自分自身を守るための行動なのかなとも読みながら感じました。
4回登場する下人のにきびと若さの象徴
『羅生門』の下人の右のほほにはにきびがあります。
さて、このにきび、なんと『羅生門』の中で4回も登場するのです!
〇羅生門の医師団に座ってぼんやり雨が降るのを眺めていたとき
〇羅生門のはしごを登って楼の上の様子をうかがっていたとき
〇老婆が言い訳をするのを聞いているとき
〇老婆から着物を奪うとき
短い小説の中になぜこんなにもにきびを登場させるのか。
このにきびが一つ、この下人の若さの象徴であるからと言われています。
下人はこの右ほほのにきびをずっと気にしています。
大事な場面ではついつい触ってしまうほどに。
これってなんだかわかりますよね。
自分も若かったころはにきびが気になって気になって、なんとかなくならないかとつい触っていたものです。
解き放たれる下人
上記した4回のにきびが出る場面。
一つだけほかと異なる場面があります。
それは一番最後の老婆から着物を奪い取るときです。
「老婆の話が完(おわ)ると、下人は嘲るような声で念を押した。そうして、一足前へ出ると、不意に右の手を面皰(にきび)から離して、老婆の襟上(えりがみ)をつかみながら、噛みつくようにこう云った」
このあとに言うのが、あらすじにも書いたセリフです。
それまでは、にきびは下人が気にしているものとしての描写でしたが、最後だけは、下人がにきびから手を離します。
「にきびから手を離す」この行為が、それまでの下人から解き放たれたことを表しています。
このときに下人はよくも悪くも、精神的に一つ大人になりました。
下人はそれまで、生きるか死ぬかのときに、
「盗人になるなんて悪いこと……」
なんて気持ちがどこかにあって踏ん切りがつきませんでした。
でも、老婆に会い、話を聞きながら、善悪だけではないこと、生死の問題に行き着くのです。
正しいことと悪いこと…比較すれば正しいことがいいのだろうと当然に思います。
でも、正しいことだけでは生きていくことができない。
いったいそういったときに自分だったらどうするのでしょうか。
おわりに
芥川龍之介の『羅生門』。
人間の本質というか、深い部分が見えてくるおもしろい小説でした。
改めて考えてみると、人間のエゴ、利己的な部分っていうのは誰しも持っているもの。
私にもそういった利己的なところはあるし、周りを見ていても、自分のことが何よりも一番!周囲の迷惑なんて関係ない!なんて人もいます。
そういった人間の生き方という部分でもう一度考えるきっかけとなる作品でした。
『羅生門』のような究極の場面におちいることはないと思いますが、やはり誰かに優しくあれて、自分も幸せというのが理想ではありますね。
そうするためには、身体的にも精神的にも自分に余裕がないとできないのだろうと感じます。
さて、次は芥川龍之介の『藪の中』を読みたいなと思います。