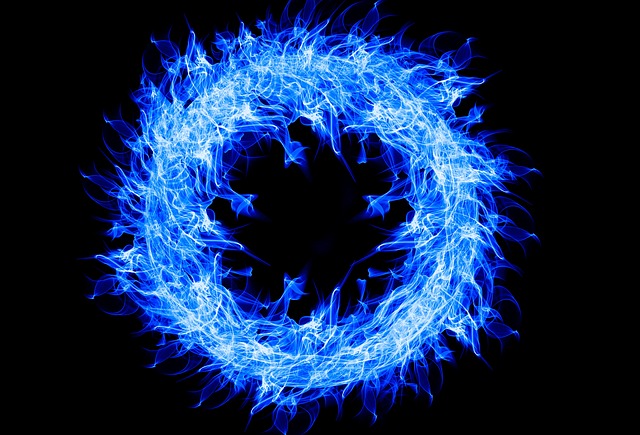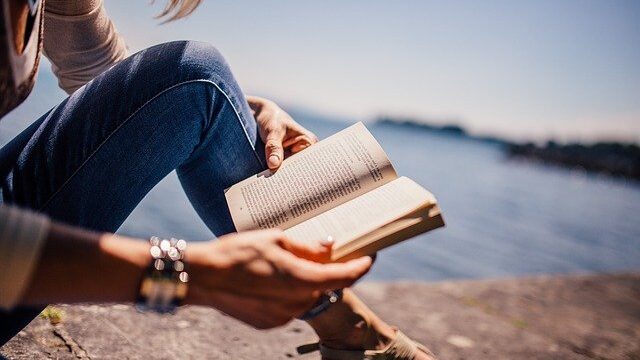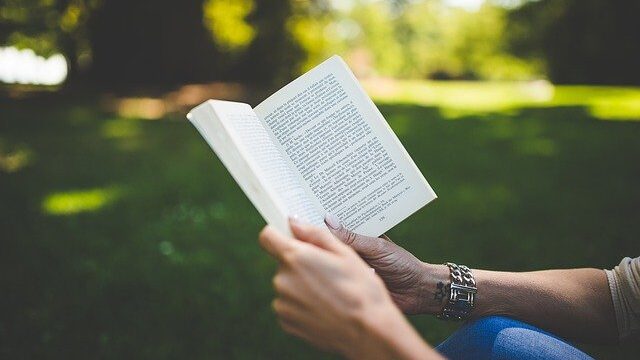どこにでもいる17歳の少年を犯罪に駆り立てたものはなんだったのか。
今回読んだのは、貴志祐介さんの『青の炎』です!
1999年に出た小説ですが、いま読んでもとてもおもしろく、切なくなる物語です。
時代がかなり違うので、当然、携帯もないし、少年法も改正されています。
そこを踏まえた上で読むのがいいですね。
2003年には、嵐の二宮くんが主演で映画にもなりました。
ここでは、『青の炎』のあらすじや感想を紹介していきます。
Contents
『青の炎』のあらすじ
櫛森秀一は、湘南の高校に通う十七歳。
女手一つで家計を担う母と素直で明るい妹との三人暮らし。
その男が現れるまでは、慎ましやかでも幸せな日々を送っていた。
男は、曾根といい、母が十年前に再婚し、曾根の暴力などが原因で、すぐに別れることになった男だった。
曾根が秀一たちの家に居座るようになってから、家族三人は怯えて暮らすようになる。
曾根は、酒を飲み、ギャンブルにふけり、機嫌が悪いと物にあたったり、暴言を吐いたりする。
秀一は現状を、警察や弁護士にも訴えた。
しかし、警察は家庭内のこととして、事件が起きないと動いてくれない。
弁護士は親身に相談に乗ってくれたが、曾根を排除する決定的な力を持っていなかった。
曾根への怒りを内に宿した秀一。
ある日、曾根が妹の部屋に押し入ろうとし、母にも性的暴力を振るっていることを知った。
秀一の中の怒りは、青い炎となって吹き荒れる。
秀一は、曾根を『強制終了』させることを決意するのだった。
どこにでもいる少年だった
秀一はどこにでもいる17歳の少年だった。
友人たちとも冗談を言い合いながら過ごし、貧しいながらも家族三人で幸せだった。
望んだのはそんな平穏な日々。
それがたった一人の男の登場で覆されます。
なぜこんなことになったのか。
ふつうに生活を送りたいだけなのに。
読者として、読んでいて切なくなります。
きっと、曾根が登場しなければ、成績もいい秀一のことだから、奨学金でも借りて大学に行くのか、家族のために働き出すのか。
どちらにしても、家族で仲良く暮らしていたのだと思います。
紀子とも、いい関係を築いていったのかな。
ゲイツから購入するお酒も、小説の中のように、次から次へと飲んでしまうということはないでしょう。
おかしい人物が事件を起こす場合、
「やっぱり」
とか、
「あぶない人がいるもんだ」
と感じますが、秀一のようなふつうに生きてきて、ふつうに生きることを望んでいる人が、そうせざるを得なかった、そこを見事に描いていて胸が痛くなります。
最後の一押しをしたもの
秀一は、小説の序盤ですでに曾根に対する殺意を抱いています。
どうやったら曾根を排除することができるか。
しかし、それには誰にもばれないようにしなければならない。
そんなことを頭の中で思い描きながらも、現実には、そんなことはできないのだと理解していました。
苦しくても、耐えて耐えて生きていこうとしています。
そんなとき、秀一は、とある英語の歌詞を耳にします。
「last straw」
直訳すると「最後の藁」となる不思議な言葉。
最後の藁は、荷物を持って歩くラクダの背骨を折ってしまうものだと。
最初は、意味がよくわからなかった秀一だったが、軽いはずの最後の藁は、ぎりぎりのところで均衡を保っていたものを崩してしまうきっかけなのだと理解します。
そして、曾根への怒りに対して、理性で抑え付けていた秀一でしたが、その最後の藁がついに目の間に。
単純に、怒りのままに曾根を排除するのではなく、ぎりぎりまで秀一が耐えようとしていた姿。
この描き方が『青の炎』の見事な部分でもあると感じます。
すべてを焼き尽くす青の炎
秀一の友人である大門。
彼はなにがあっても怒らない。
なぜなら彼自身がそう決めているから。
怒りは炎となり、相手を焼いてしまう。
それだけでなく、その怒りの炎は周囲へも広がり、ついには自分さえも燃やし尽くしてしまうのだと。
秀一に生まれたのは青い炎。
ふつうの赤い炎よりも、より高温で、よりすべてを燃やすことができる。
一度、火をつけてしまったら後戻りはできない。
それでも、秀一にはどこか、幸せが待っていてほしいと感じずにはいられません。
おわりに
もともと、少年犯罪に関する小説が読みたいと思って検索したときに出てきた本です。
少年犯罪というと、暴走族だったり、ちょっとやんちゃな人生を送っている人が起こすものというイメージがあります。
でも、実際には誰にでも起こりうること。
秀一のように、ふつうに見えるところにだって。
だから、そうした犯罪がなく、生きている人は、それ自体がとても幸せなことです。
貴志祐介さんって、『新世界より』の印象が強かったので、こうした小説もあったのだと新しい発見でした。
またほかの作品にも手を伸ばしていこうと思います。