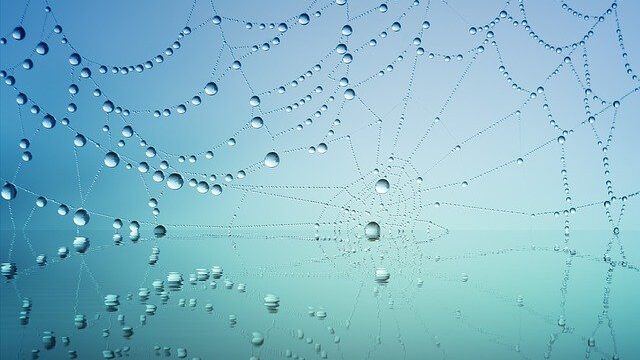自分の体にコンプレックスを持つ人ってけっこういると思います。
私だと低い身長とか、薄い髪の毛とか、昔は気になっていたなと。
この人の場合、人並外れた長い鼻。
もう何の小説かおわかりですね。
今回読んだのは、芥川龍之介の『鼻』です!
短い小説ながら、考えさせられることの多い名作です。
ここでは、『鼻』のあらすじや感想を紹介していきます。
Contents
『鼻』のあらすじ
池の尾に住む50歳を超えた禅智内供。
彼のその長い鼻のことを池の尾で知らない人はいない。
長さは5,6寸あり、唇の上から顎の下まで垂れさがっており、形も太く、細長い腸詰のようだった。
内供は、以前からこの鼻に苦しんでいたが、自分で鼻を気にしているのを人に知られるのが嫌だったので、気にならないような顔をしていた。
しかし、長い鼻はとても不便。
食事をするのにも鼻が膳に入ってしまうので、弟子に板を使って持ち上げてもらわないといけない。
また、それ以上に、この鼻によって傷つけられる自尊心のために苦しんでいた。
内供は自尊心を回復しようと、鼻が短く見える角度はないかと工夫を凝らしたり、自分と似たような鼻を持った人間がいないかと探してみたりしていた。
だが、いずれも徒労に終わり、途方に暮れるばかりであった。
そんなある日、弟子の一人が都で「鼻を短くする方法」を教わってきた。
その方法というのは、お湯で鼻をゆでて、その鼻を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。
弟子が教わってきた方法を試すと、驚くべきことに、長かった鼻は嘘のように縮んでしまった。
これでもう自分を笑うものはいないと、内供は満足し、何年もなかったくらいにのびのびとした気分になった。
しかし、2,3日経つうちに、内供はこれまで以上に、周囲の人が自分の顔を見て笑っていることに気づいた。
最初は、自分の顔が変わったからだと考えたが、それだけでは理由がつかない。
人々は、内供の鼻が普通になったのを見て、内供の不幸に同情をしていた。
一方で、その不幸を切り抜けたことで、何となく物足りないような気持ちを感じているようだ。
人々の勝手さに腹を立てる内供であったが、ある日目を覚ますと鼻は元の長さに戻っていた。
そのとき内供には、鼻が短くなったときと同じような晴れ晴れとした気持ちが湧き上がっていた。
「これでもう笑うものは誰もいない」と、内供は心の中で自分にささやいたのであった。
コンプレックスを受け止めることはできるのか
長い鼻にコンプレックスを抱いていた内供。
それはそうですよね。
他人とは明らかに違う長い鼻。
見た目にも異様で、生活する上でも不便でしかたがない。
だから、内供が自尊心を傷つけられて、苦しむというのはとてもよくわかる話です。
多くの人は、なにかしらそういった部分を抱えているものです。
それは、他人から見ればとても些細なことであっても、その人にとっては非常に真剣で大きなもの。
小説の中では、内供は鼻をなんとか短くできないかと試みて、ついには成功を果たします。
でも、そこで万々歳とはいかないのが物語というもの。
今度は、短くなったことによって、周囲の反応が変わり、またもや自尊心が傷つけられる。
鼻が長くても、短くても、内供が苦しむことには変わりなかったというわけです。
では、内供はどうすればよかったのか。
その長い鼻でさえも、自分なのだと認めることが大事だったんでしょうね。
それって実際すごく難しいんですけど。
特にここまであからさまに周囲と違うと現実的に大変です。
だけど、私たちが生きていく上で、そうした内面での受け止め方というか、納得のしかたって非常に重要です。
冒頭にも書いたように、私も身長だったり、親譲りの髪の薄さに悩んだ時期もありました。
今だって、あと5cmほしいと思うこともあります。
でもそれって、ないものねだりで、意味のない行為なんですよね。
気になるのは、自分がその自分を認めて上げることができていないからだとも感じます。
実際、自分が思うほど周囲は気にしていない。
内供も、誰よりも自分自身が自分のことを認めていなかったのではないか、と。
もし、認めることができていたのなら、鼻が長くても短くても、自分は自分と思えたでしょうし、鼻が短くなったときに、これほど周囲の目が気にならなかったのでしょう。
人間はいつも矛盾した感情を抱えているもの
人間の心には互に矛盾した二つの感情がある。勿論、誰でも他人の不幸に同情しない者はない。所がその人がその不幸を、どうにかして切り抜ける事が出来ると、今度はこっちで何となく物足りないような心もちがする。少し誇張して云えば、もう一度その人を、同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうしていつの間にか、消極的にではあるが、ある敵意をその人に対して抱くような事になる。
(芥川龍之介『鼻』より)
小説の後半で出てくる言葉です。
これは、内供の鼻が短くなったあとも、より一層、小ばかにするように笑う人々がいることに対する言葉です。
不幸な人、苦しんでいる人に対して、同情の念が起きるのは自然なこと。
一方で、その人がその問題を乗り越えたり成功したりすると、素直に喜べないのも人間なんですね。
人間のそうした醜い感情をうまく表現したのが、この『鼻』という小説なのだと感じます。
とはいえ、これもまた他人ごとではないんですよね。
読んでいて、自分の中にだってそういった部分があるということを認めざるを得ません。
仕事をしていたって、いつもあまり仕事がきっちりできない人が、たまにすごくうまくいくと、それを素直に喜べない。
どこか、あらを探してしまうような感情がやっぱりあったような気もします。
これって、きっと、その人がうまくいかないことで、見下すような気持ち、それに嫌な言い方ですが、多少なりとも満足する気持ちがあったのかもしれません。
短い小説なのに、がっつり読者の内面も引っ張り出されるようで、深い物語でした。
おわりに
芥川龍之介は、この『鼻』にしても、『羅生門』にしても、人間を描くことがすごく上手です。
その分、自分自身の嫌な部分も一緒に暴き立てられるようで、読んでいてきついなってところもあるのですが。
だからこそ、自戒にもなって、自分を見つめ直すいい機会にもなるのかなと感じます。
特に芥川龍之介は、一つ一つの作品も短いので挑戦しやすくておすすめです。