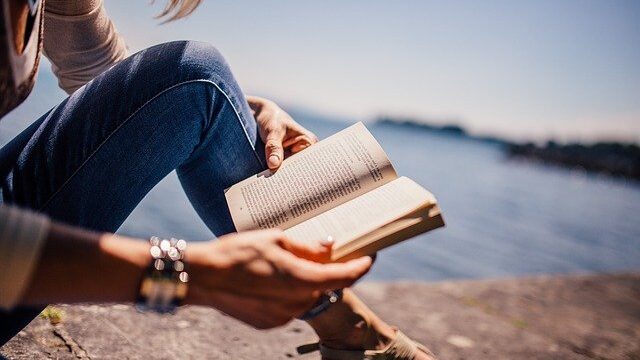「死に至る病」という言葉を単純に聞くとどんな病が思いつきますか。
今では、延命率もかなり高いですが、ぱっと、癌が思い浮かぶ人もいれば、不治の病のようなものをイメージする人もいるでしょう。
ただ、この本に書いてあることはかなりがっつりと違う答えです。
今回読んだのは、キェルケゴールの『死に至る病』です!
『死に至る病』は、「死に至る病とは絶望のことである」と、「絶望とは罪である」の二編からなる哲学書です。
はい、もう章のタイトルからわかるとおり、「死に至る病=絶望」だと最初から訴えています。
絶望ってものがどういうものなのかってことがひたすら書かれているんですね。
本当にどれだけ絶望って書くんだよって言うくらいに、どこを読んでも絶望ばっかり。
そして、キリスト教の教義にも触れた内容であり、それがかなり話を難解にさせていきます。
正直、私も何度も挫折しつつ、眠くなりつつ何とか読み切ったという感じです。
さて、ここではそれでも多少なりとも、『死に至る病』の内容をわかりやすく紹介できればなと思います。
ちなみに、ここでの引用元は、岩波文庫版の『死に至る病』第94刷のものになります。
Contents
キェルケゴールとはどんな人か
キェルケゴールは、セーレン・オービュ・キェルケゴールと言います。
1813年5月5日に生まれたデンマークの哲学者です。
キリスト教徒であり、その著書にはその思想がしっかりと反映されています。
キェルケゴールは、コペンハーゲンの富裕な商人の家庭の7人兄弟の末っ子として誕生します。
27歳の時に一度婚約までするものの、それを翌年には破棄し、生涯独身を貫いています。
その相手はレギーネ・オルセンという当時(1840年)17歳の女性でした。
キェルケゴールの求婚を、レギーネは受けますが、その約一年後、彼は一方的に婚約を破棄します。
この婚約破棄の理由については諸説ありますが、はっきりとはしていません。
キェルケゴールは、父親の希望に添って大学で神学を専攻し、牧師になるという考えも抱いていましたが、30歳の年に『これか=あれか』をもって、デンマークの思想界にデビューします。
これ以降、『反復』、『不安の概念』、『瞬間』など、矢継ぎ早に多くの著書を世に送り出していくことになります。
『死に至る病』をざっくりと説明すると……
すごく簡単に言ってしまうと、『死に至る病』は、キリスト教を信仰することの大切さをうたった本になります。
第一編の「死に至る病とは絶望のことである」では、いろいろあるけど、人間ってみんな絶望している生き物なんだよってことが書いてあります。
絶望の種類をいろんな形態や段階で紹介しながら、絶望しない人間はいないのだと。
キェルケゴールの考えによると、自分自身が絶望していることを意識している人も、意識していない人も絶望しているってことになります。
第二編である「絶望とは罪である」に入ると、「死に至る病=絶望」の対処法はキリスト教の信仰であると断言します。
神の前に自己を捨てることが信仰であり病の回復に繋がるのだと。
ということで、ここから先はもう少し細かく、『死に至る病』の内容に触れていきます。
自己とはなにか
さあ、本題は「絶望」です。
でも、その前に、大切な概念として、「自己」という言葉が出てきます。
まずは引用から。
人間は精神である。精神とは何であるか? 精神とは自己である。自己とは何であるか? 自己とは、自己自身に関係するところの関係である、すなわち関係ということには関係が自己自身に関係するものなることが含まれている、――それで自己とは単なる関係ではなしに、関係が自己自身に関係するというそのことである。
(キェルケゴール『死に至る病』P20より)
これ初っ端からよくわからないですよね。
これが第一編の冒頭に書かれている言葉です。
翻訳によって多少の違いはありますが、おおむねこういった内容でした。
絶望の話をしていく前に、キェルケゴールは、最初に自己の定義を行ったんですね。
キェルケゴールのいう「自己」とは関係のことです。
そして、自分自身に関係しているところの関係。
もうややこしいですね。
なにからも関係しない人っていません。
自分自身は、いろんなものからの関係によって、形作られており、その自分自身と、自分に関係してくる関係をひっくるめて自己と言っています。
自己を考える上で、「無限性と有限性」、「時間的なものと永遠なもの」、「可能性と必然性」があります。
人間は無限性(想像力)の中で生きることもできるし、現実を見ることもできる。
肉体のように、いつかは滅ぶものと考えることもできれば、精神のように永遠性を求めることもできる。
自分のできることを見据えることもできれば、更なる可能性に目を向けることもできる。
こうした3つの二極間で、自分がどう生きていくのか、どのバランスで生きていくのかを決めることで、本当の自己となることができます。
絶望とは死のことではない
ようやく絶望の話です。
キェルケゴールは、人間は誰しも絶望するのだと言います。
人間は生涯をかけて、自分自身と付き合っていく生き物だからです。
キェルケゴールの考える絶望にはいろんな種類や段階があります。
たとえば、「自己自身であろうとする絶望」と、「自己自身であろうとしない絶望」の二つがあります。
人間って、どちらかには当てはまりますよね。
うまくいかなくて、自暴自棄になったり、投げやりになったときなどにも絶望は生まれます。
逆に自分はこうしたい!こうなりたい!という理想に燃えている人、これもまた、そこに至れない自分に絶望するのだとも言います。
絶望ってとにかくいたるところに転がっているんです。
キルケゴールは、この絶望こそが、人間にとってもっとも恐るべき「死に至る病」であるといいました。
ただ、あくまで「死に至る病」なんですよ。
「絶望=死」ではないんですね。
キェルケゴールは、一般的に、「死に至る病」というと、致命的な病のことを指して言われているが、キリスト教の立場からすると、死とはそれ自身が生への移行であると語ります。
地上的な肉体的な意味での死に至る病は考えられないのだと。
むろん死が病の終局に立っているにはちがいないが、しかしその死が最後のものなのではない。死に至る病ということが最も厳密な意味で語らるべきであるとすれば、それは、そこにおいては終局が死であり、死が終局であるような病でなければならない。そしてまさにこのものが絶望にほかならない。
(キェルケゴール『死に至る病』P28より)
続けてキェルケゴールは、「死に至る病」は、断じて人は死ぬことはないと言い、肉体的な死では終わらないのだとしています。
「絶望」とは死にたいけれども死ぬこともできずに生きていく状態のことです。
肉体的な死よりももっと高尚な世界での苦しみであると考えられます。
絶望の二つの例
『死に至る病』では、帝王になろうとした男性と、恋をした女性の絶望を例として取り上げています。
まずは帝王になろうとした男性です。
本の中では、支配欲のある男とされています。
彼は帝王になりたい、でも帝王にならない場合、彼はそれについて絶望をするといいます。
なりたくてなれないなら、たしかに絶望するような気がします。
でも彼は、帝王になれなかったことに絶望をしているわけではないのです。
すなわち彼は帝王にならなかったが故に、彼自身であることが絶ええられないのである。だから彼は本当は自己が帝王にならなかったことに絶望しているのではなしに、帝王にならなかった自己自身に絶望しているのである。
(キェルケゴール『死に至る病』P30より)
もし、彼が帝王になっていたならば、彼の自己は喜びであり、そうならなかったことが耐えられないというのです。
あくまで帝王になれなかったことではなく、自己に対する絶望であり、自己自身を抜け出ることができないことへの絶望なのであると。
自己自身について絶望していることの例として、若い乙女の恋を紹介しています。
彼女は恋人が失われたこと(死んだないし、彼が彼女を裏切ったこと)について絶望している。
彼に愛されていた自己であったはずなのに、彼のない自己でいなくてはいけなくなったことによって絶望します。
本来は、彼の存在で充実していた部分が、空虚となり、嫌悪すべきものとなった。
それは、彼に裏切られた人間であることを彼女に思い起こさせるものであるから。
こうして見てみると、願望や理想があるから絶望があるのかという気持ちにもなってきます。
絶望の諸段階
絶望であることを知らない絶望
キェルケゴールは、絶望には諸段階があるとされます。
それは自分が絶望であることを知らないことから始まります。
「自分が絶望であることを知らないでいる絶望」はもっともレベルの低い絶望とされます。
と言われても、ほとんどの人は、自分が絶望をしていると思わないですよね。
キェルケゴールも、これが普通の人に多くある状態だとしていいます。
日常的に生きていて、楽しいこともうれしいこともありますし、学生時代だったら部活動やサークル活動に必死になっていた記憶もあります。
これが動物であれば、絶望をしないのかもしれません。
でも、人間である以上、いつかは必ず絶望を自覚するようになるというのです。
絶望であることを知っている絶望
次の段階は「自分が絶望であることを知っている絶望」です。
これが一番、絶望っぽい絶望な気がしますよね。
「私は絶望しているのだ」
という自覚があるわけです。
でも、キェルケゴールは、本当にその人が絶望というものをわかっているのかは疑問であり、わかっていなければ、その人が考えているよりも、もっと多くの絶望を持っているということを教えないといけない、なんて言ってるんです。
これには次の2つの段階に分かれます。
それは「弱さの絶望」と「強さの絶望」です。
「弱さの絶望」とは、絶望して自己自身であろうとしない絶望です。
また、絶望していかなる自己でもあろうと欲しないこと、更にいくと、自己自身とはもっと別の人間でありたいと欲すること、新しい自己でありたいと願うことでもあります。
「強さの絶望」は、絶望して自己自身であろうと欲する絶望です。
「弱さの絶望」とは逆に、自我の絶対性をもつ傲慢な態度です。
この絶望も救われる道があるのに、その救済ですら、自分自身が望む形でなければいけないとしています。
もしも、自分が望む形以外の救済が必要であるとしても、その救済を受けるくらいなら、苦悩のままにいたほうがいいと考えるのです。
絶望から救われるためには
人間は絶望をしている。
自覚があっても、自覚がなくても。
自己自身であろうとしても、自己自身でないことを欲していたとしても。
キェルケゴールによれば、誰もが絶望をしています。
その絶望から救われるためにはどうすればいいのか。
キェルケゴールは、その答えを「信仰すること」だとします。
苦悩で満ち溢れた世の中で、神の意志に耳を澄ませることが大切です。
そして、それを体現しようと生きるとき、私たちは絶望から解放されるのだと。
神の意志に忠実に生きていることで、人は安心感を手にすることができる。
これこそが、絶望から解き放たれて生きることになるのだと言います。
反対にこの絶望を感じることがないと、人々は神を求めはしないといいます。
これはなんとなくわかりますね。
キリスト教に限らず、仏教だって、苦しいことがあるから神頼みをするわけですもんね。
濁世が苦しいから信仰をして、救いを求める。
信仰が生まれるその形は、どの宗教でも同じなのかなと感じます。
キェルケゴールの考えでも、絶望を感じて初めて、人々はそれから解放されようと神の意志を探し始めるのだとされています。
『死に至る病』の気になる名言
さて、『死に至る病』は、完全に理解しようとすると難しすぎてどうにも苦しい。
でも、一つ一つの文章を見ていくとかなりおもしろいんですよ。
ということで、私が読んでいておもしろいなーと思った言葉をいくつか紹介して終わりたいと思います。
思うに信仰者とは恋する者である――だが恋するすべての人々のうちで最も熱烈に恋している者であっても、信仰者に比すれば、その熱情の点ではただの未熟な若者にすぎない。
(キェルケゴール『死に至る病』P168より)
信仰を持つ人は恋する者だと。
恋の熱情ってかなり恐ろしく強いものがありますよね。
想い焦がれる相手で心は染め上げられ、それ以外に目に入らない、その人がすべての行動基準になるって人だっているほどです。
しかし、信仰者は、その人たちの熱情をも超えるのだと言います。
悪魔的なるものはそれ自身に一貫的であり、悪の一貫性のうちに立っているものであるが、故に、彼もまた全体を失わなければならないからである。
(キェルケゴール『死に至る病』P176より)
このあともいろんな言葉が続くのですが、悪魔的なものにはそれはそれで一貫性があるのだという話です。
悪といわれる人でも、悪であるためには、悪であり続けなければいけない。
一たび、善の行いをしてしまうと、一貫性を失い、もとの自分には戻れなくなってしまうのだと言います。
だから、善の祝福を恐れ、悪であり続けようとするのだと。
続けて、
ただ罪の継続のなかでだけ彼は彼自身であり、かつ彼自身であるという感じを持ちつづけることができる。
(キェルケゴール『死に至る病』P176より)
これも現実に置き換えてみると、なんだかすごくわかるような気がします。
悪い人であるということ、強い自分を見せようとすること。
そのときに、そこから外れた行動をしてしまうと、一気に空気が萎むように、それまでの形を維持できなくなることってあると思います。
良くも悪くも、一貫性というものは、自己を保つためには必要なのかなと感じました。