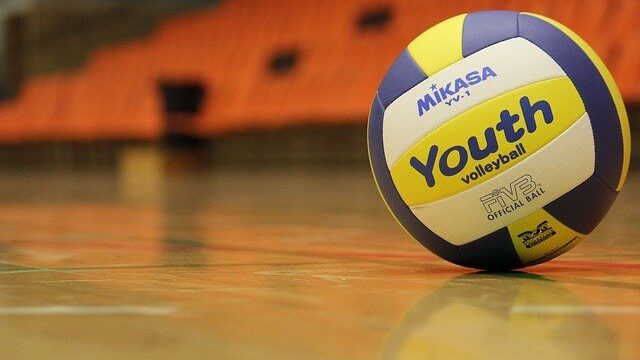16歳のときって自分はなにをしていただろうか。
高校一年生から二年生。
毎日、特に当たり前のように授業に出て、部活に出る。
帰りには買い食いをしたり、本屋で立ち読みをしたり。
将来なんてものは考えてもなかったな思います。
でも、その16歳という年齢でこれだけの小説を書く人もいるというから驚きです。
今回読んだのは、青羽悠さんの『星に願いを、そして手を。』です!
第29回小説すばる新人賞受賞作になります。
著者の青羽さんは2000年生まれで、受賞した当時、なんと16歳という若さでした。
夢とは何か。夢とどう向き合うのか。そんなことを考えさせられる小説です。
ここでは『星に願いを、そして手を。』のあらすじや感想を紹介します。
Contents
『星に願いを、そして手を。』のあらすじ
中学三年生の夏休み。
宿題が終わっていない祐人は、幼馴染の薫、理奈、春樹と科学館に集まっていた。
そこは、プラネタリウムに併設された図書室で、祐人たちは毎年の勉強会をおこなっていた。
四人が勉強していると、乃々さんがカルピスを持ってきてくれる。
館長の作った少し薄いカルピスに文句を言いながら四人は楽しく過ごしていた。
館長は四人に星の話、宇宙の話を楽しそうに語り、四人もまた宇宙への強い関心を持つようになる。
四人でいれば最強だと信じて疑わなかった。
やがて四人は成長していく。
だが、あるきっかけから、四人は距離を置くようになってしまう。
祐人は昔思い描いていた夢を諦め、東京の大学を卒業後、故郷に帰り、公務員となった。
地元に帰ってからも、科学館には足を運ばず、避けていた祐人。
そんなある日、館長が亡くなったとの連絡を受ける。
祐人は、数年ぶりに薫、理奈、春樹との再会を果たすのであった。
”夢”というもの
『星に願いを、そして手を。』の重要なものが”夢”です。
四人は宇宙に憧れ、そこから強いつながりを感じていました。
具体的にどんな夢なのかってわからないですが、夢を見て、夢を追って生きていた。
でも、子供のころに見ていた夢を大人になっても見続けることができる人ってやはりそんなにはいないものです。
夢を諦めてしまった人もいれば、今も夢を追い、その道が正しいのか悩む人もいる。
夢のために走り続けたけれど、失敗をしてしまった人だっている。
「夢を見続けるのは簡単じゃない。夢から覚めないまま、でも夢を見ていることすら忘れている人がたくさんいるんだ」
(青羽悠『星に願いを、そして手を。』P289より)
この言葉もとても納得のいくものでした。
どこか夢を見ているのに、その夢が自分の中にくすぶり続けているのにそれに気づかない。
そのことを忘れている。
ああそれは自分にも言えることだなとまっすぐに胸の中に入ってきたように感じました。
夢というものは、希望にあふれ、美しいものであり、残酷で悲しいものでもあるのだなと思わされます。
大人になるということ
『星に願いを、そして手を。』の中では、高校生で館長の孫である直哉。
社会人になったばかりだったり、大学院に通ったりしている祐人たち。
館長や奥さんの乃々さんたちといったずっと上の世代。
そうした三世代が登場していてそこもこの小説の特徴かなと思います。
純粋にまだ夢を追いかけられる少年時代から、現実が見えてくる20代。
そして、夢を叶えたり夢に破れたりして、夢との距離が固定されていく世代と。
大人になるって大変なことですよね。
私自身、ちゃんとした大人になれているのかってかなり疑問はあるのですが、それでも、
「大人なんだからちゃんとしないと」
「大人ならこういう場合こうしないと」
っていったものにがんじがらめにされて、けっこう窮屈な生き方をしている人も多いと思います。
もちろん子どものころが楽だったわけではなく、そこには人間関係も、やれ受験勉強だ、やれ将来だと追い立てられるものはありました。
それでも、未来への希望というか、まだどの道でも選びやすい時期だったのだと四十近くになると感じます。
「大人は、大変だよ。大人になっても何も成長しないのに、変わることを求められる。自分が大人であるためにって、自分を取り繕わなきゃいけない」
(青羽悠『星に願いを、そして手を。』P19より)
まさにこの言葉どおりで。
当時16歳の若者がこんな文章を書いていることにかなり衝撃でもあるんですけどね。
おわりに
小説すばる新人賞受賞作品を読み進めていますが、その中でもかなり考えさせられて好きな作品でした。
特にこの本は、ほかの本よりも心にぐっとくる言葉がたくさんありました。
意識的にそういった文章を作っているのかなとも思いますが、読んでいて、
「本当にそうだよね!」
と共感できる部分も多く、物語に入りやすいなと感じます。
この記事を書いている時点で複数の短編と、二作目の長編が出ているようなので、今の新人賞ブームが終わったらそちらも手を伸ばしたいと思います。