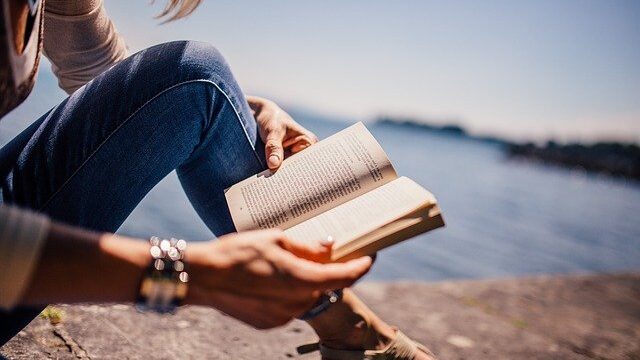何かに人生を捧げることができる人ってどれくらいいるのだろうか。
少なくとも私は、自分のすべてを捧げてもいいと感じる存在に出会ったことはない。
もちろん大切なものはいくつもある。
妻や娘は何よりも大切だし、趣味の読書の時間もできるだけ確保したい。
学生時代は好きなアイドルだっていたし、スキューバダイビングにのめり込んでいたときもある。
しかし、それでも、自分の生きる上での中心、本書の言葉を借りれば背骨となるものって果たしてこれから先も出会うことはあるのだろうか。
今回紹介するのは、宇佐見りんさんの『推し、燃ゆ』です!
第164回芥川賞受賞作ということで2020年~2021年、大きな話題となっていました。
「推しが燃えた」
という独特の表現から始まる本書。
アイドルを推して推して推しまくる主人公に圧倒されます。
Contents
『推し、燃ゆ』のあらすじ
主人公のあかり。
アイドルグループに所属する上野真幸を推していた。
「推しは私の背骨だ」
そう表現するほどに、あかりは推しを推しているときだけ生きている実感を持てていた。
生活のすべては推しを中心に動き、推しが出た番組やラジオはすべてチェック。
推しが何を考え、どう行動しているのかを解釈することに力を費やしていた。
しかし、ある日、推しがファンを殴ったとされて炎上する。
なぜ推しがファンを殴ったのかはわからない。
だが、その影響はあかりの実生活にも大きな影響を与えることになっていく。
「推し」を推すということ
私はこの『推し、燃ゆ』が芥川賞を受賞してからもしばらくは手に取ろうとしなかった。
きっと芥川賞を受賞するくらいだからいい本なのだとは感じていた。
しかし、どうにも「推し」という言葉が引っかかっていたのだ。
「推し」というとぱっと浮かぶのはアイドルグループとそれを追いかけるファン。
実際にそれで間違いではない。
だからこそ、自分には縁のない世界であり、そこまで興味がわかない部分もあったのだと思う。
職場の先輩にもアイドルが好きな人がいる。
その人は、AKB48に始まり、この十年でいろんなアイドルに興味を移しながら、
「今は地下アイドルが一番熱い!」
と豪語し、ライブにもよく通っているようである。
趣味は人それぞれだと思いながらも、CDを何十枚も買うのには理解が及ばないし、チェキを取るのに1000円とか払うのも自分からすると不思議な感覚。
『推し、燃ゆ』の中でも、
十枚買うごとに好きなメンバーと握手できるから幸せなシステムだと思う。
(宇佐見りん『推し、燃ゆ』より)
というセリフがあるが、握手券のために同じCDを十枚……やっぱりよくわからない。
そんな気持ちで『推し、燃ゆ』を読んでいたが、読むにつれ、推しとファンとはそんな簡単なものではないのだと気づかされる。
主人公であるあかりは、発達障害を持っている。
他の人と同じようには行動することができず、周りが平然とこなすことも、何度も確認をしながらなんとかこなす。
いくつものことを言われると、そのうちいくつかが抜け落ちていってしまう。
そんなあかりを周囲は冷やかな様子で見ている。
それは家族も同様。
いろんな重圧を感じながら、苦しい呼吸の中、窒息しないように必死に生きていく中、唯一あかりが自分でいられるのが推しを推すときだったのである。
推しを推すときだけあたしは重さから逃れられる。
(宇佐見りん『推し、燃ゆ』より)
この短い一文にどれだけの想いが込められているのだろうか。
自分がふつうではないとわかっていながら生きるということはつらいことだと思う。
それは仕方がないことだと思おうとしても、それを周囲が同じように感じてくれるわけでもない。
日々、悪意なく投げつけられる反応にすり減らされていくとき、自分の居場所となったのが推しなのであれば、それは必要なことなのかもしれないと感じた。
もちろん、推しを推すという行為は人によって意味が異なる。
単純に楽しいからという人もいれば、自分が育てているような感覚を持つ人もいる(私の先輩はこちら派)。
推しの存在が生きがいで人生という人もいるだろう。
推しを推すことが自分の中心であり背骨であるというあかりは、きっと推しがいなければ生きていくことが難しかったのだと思う。
発達障害と家族
『推し、燃ゆ』を読む前は、推しとファンの話だと思っていたが、それ以上に、発達障害の少女とその家族に目がいく作品であった。
あかりの母親は、あかりと姉に対して、同じように厳しく教育をしようとする。
でも、あかりにはいくら教えても母親が望むようにはうまくすることができない。
中学、高校と進学してもそれは同じ。
母親はどこまでもあかりにふつうの人であることを望んでおり、できないあかりに失望を感じていく。
親の失望ほど、子どもを暗い気持ちにさせてしまうものはない。
高校を中退することになってしまったあかり。
就職をするように促されるも、推しが生活の中心となっているあかりとは、やはりどこかずれがある。
就職先を探すために何回か電話をしたというあかりと、履歴書は書いたのか、本気で就職しようとしているのかと責め立てる母親。
本書からはどこまで本気で就活をしたのかはわからないが、あかりにとっては、ハードルが高いものであったことは間違いない。
父親も父親で、働かないのであればいつまでも家に置いておくわけにはいかない、働かないと人間は生きていけないのだとあかりを諭そうとする。
それに対して、「じゃあ死ぬ」と答えるあかりとの齟齬が、この家族のずれをはっきりと示していた。
もし、家族があかりの障害をしっかりと認識し、それを理解した上で寄り添うことを選んでいたらこの物語はどうなっていたのだろうか。
そもそも、推しを推すというあかりの生きる意味自体が必要なくなっていたかもしれない。
身体を壊すほど、自分を追い詰めてまで推しを推すあかりの姿は一種異様なものがある。
でも、そうなった背景には家族があり、周囲の反応があり、そこ以外にあかりが生きていく場所がなかったということなのだと思う。
いつかは推しもいなくなるもの
『推し、燃ゆ』の最後には、推しがアイドルを引退してただの人になる。
もうこれまでのように、推しを推し、愛でて、それを生きがいとすることはできなくなる。
その喪失感はいったいどれほどのものだっただろうか。
いつかは推しはいなくなるもの。
それは本書の中でもあかり自身感じていたものでもある。
推しがいなくなった世界をあかりはどう生きていくのか。
これは、人はいつかは一人で歩き出さなければいけないということを言っているようにも感じた。
現実をしっかりと見て、地に足をつけて向き合っていかなければいけない。
強くならなければいけない、と。
でも、それをあかりに求めるのはとても酷なことでもある。
自分の背骨が突然なくなってしまった。
そんな状態で何ができるのだろう。
しかし、それでも進まなければいけない。
それが生きるということだから。
大事なものを失ったとき、一人となったときに生きていくだけの力を持ちたいと感じさせられる作品でもあった。