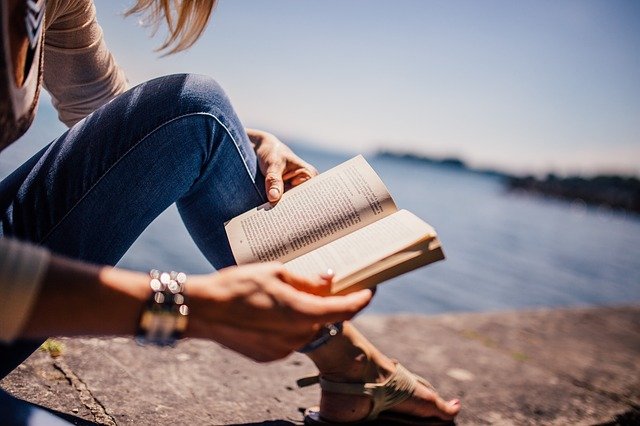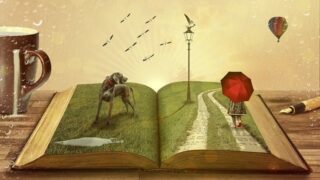どんな家に生まれ、どんな家族と過ごすのか。
それは子どもには選べないこと。
家族の変化を子どもはどう感じるのか。
胸が痛くなる小説でした。
今回読んだのは、宇佐見りんさんの『くるまの娘』です!
『推し燃ゆ。』で芥川賞を受賞した宇佐見りんさん。
受賞後、初の作品となりますが、こちらの作品も独特の世界観とタッチで、ほかの作家にはないものを感じます。
しかし、読んでいて苦しいし、どうすれば救われるのかと思わずにはいられない。
ここでは、『くるまの娘』のあらすじや感想を紹介していきます。
Contents
『くるまの娘』のあらすじ
かんこは高校に通う女子高生。
その生活は順風満帆とは言い難い。
机で居眠りをして、気づけば周りには誰もいない。
もしくは、移動教室で来た別のクラスの生徒に起こされる。
起きていられないのだ。
気付けば寝てしまい、それもいつまでも目覚めることができない。
そんなことがかんこには頻繁に起きていた。
昔はそうではなかった。
きっかけは二年前に母親が脳梗塞で入院したこと。
それ以来、母親は体と記憶に障害が残り、精神的におかしくなった。
父親は、突然、子どもたちに暴力を振るうことがある。
そんな家が嫌で、兄は大学を中退して結婚。
弟は、高校に進学するにあたり、家を飛び出して祖父宅で暮らすようになった。
昔は仲が良かったのに、今ではばらばらになってしまった家族。
残されたかんこが、独りでそんな両親を背負っていた。
ある日、父方の祖母が亡くなった。
その葬儀に向かうため、家族で車に乗って移動するも、社内には不穏な空気が充満していた。
久しぶりの再会なのに両親を避ける兄弟と、家族の姿を取り戻したいかんこ。
少しずつずれて掛け違えてきた家族の関係。
それが積み重なり、年月とともに熟成されていく。
少しのずれが、取り戻せないものとなる。
家族の問題を描いた小説ってけっこうあります。
『くるまの娘』もそうした小説なのかなと思いながら読み進めましたが、それだけではない深みがありました。
簡単に言ってしまえば、問題を抱えた家族の中で、一人の娘が心の苦悩と闘いながらなんとかしたいと願う話。
しかし、読んでいて本当に苦しい。
家族って本当であれば安らげる場所であり、そういう存在であってほしいもの。
でも、一つボタンを掛け違えて、そこをすぐに修正していかないと、ずっと掛け違えたままになってしまう。
いつしかそれは取り返しのつかないずれになって、気づいたときにはもう元に戻すことはできない。
かんこの家族はなにかあったときも、なにもなかったかのように振る舞って、なあなあにして終わらせてしまうことが多かったんですね。
父親が癇癪を起こして家族に暴力を振るっても、その少し後には日常的な会話が行われる。
母親が後遺症から発狂しても、いつものこととして、向き合わずに処理をする。
かんこのあげるどうにかしたいという声は家族には届かない。
そうして積み重なったものって、何事もなかったように装っても、確実に淀みとして溜まっていっていて、熟成され、もう本人たちでもどうしようもなくなってしまう。
ただ、もとの仲が良かった家族に戻りたいだけなのに、その願いが叶わない。
そうしたとき、どうすればいいんでしょうね。
かんこが選んだのは、自分だけの逃げる場所を見つけることでした。
そうすることで、これまでよりも、ずっと気持ちが安定して、割とふつうの生活が送れるようになる。
でも、問題はなにも解決できていない。
そうやって、自分の心と折り合いをつけながら生きていく。
それは大なり小なり、誰にでもあることですが実に苦しい。
救うのであれば全員を救えという叫び
家族の問題が取りざたにされると、そこをどうやって解決するのかという視点がつきまといます。
現実社会では、児童相談所に通報なんてことがありますね。
虐待による通報件数も、社会の意識が変わってきたこともあって、ここ数年でもぐっと増えています。
子どもを救うという観点では、私もそれは正しいのだと思っています。
でも、それはすべての人がそう望んでいることではないことも事実。
『くるまの娘』で印象的だった言葉があります。
「誰かを加害者に決めつけるなら、誰かがその役割を押し付けられるのなら、そんなものは助けでもなんでもない。」
(宇佐見りん『くるまの娘』P83より)
たとえば、親が子どもを虐待していて、子どもが保護されたとします。
「子どもを守れてよかった」
と思うのは、周囲の人間だけかもしれません。
どうして、一方は加害者として扱われるのか。
どうして、全員を救ってくれないのか。
子どもも親も助けて、その家族が平穏で幸せに生活できて、初めて本当の意味で助けなのではないのか、と。
そんなこと現実的には難しいんですよ。
でも、それを望んでいるんだろうなと感じさせられます。
私も仕事柄、家庭に問題を抱えた子どもたちと接する機会はよくあります。
子どもって、親に暴力を振るわれたり、理不尽なことをされていても、不思議と親のことが好きだという場合がとても多い。
傍から見ると、なんでと思いたくなるんですけど、家族って特別な意味があるんだろうなと。
だからこそ、片方しか救えない、加害者と被害者に分けないと考えられないことがとても苦しい。
おわりに
宇佐見りんさんの小説って、決して読みやすいわけでもない。
楽しい物語でもない。
それでも、どこか引き込まれるものがあって、読み終えたあとには、不思議な読了感が残ります。
人はどこかに安らぎや救いを求めている。
それはきっと私もそうで、それがなければ日々を生きていくことを苦しく感じているのだろうなと思います。
それが家族なのか、友人なのか、恋人なのか。
趣味の世界ということもあると思います。
『くるまの娘』を読んでいて、すごくそうした存在を改めて認識させられました。