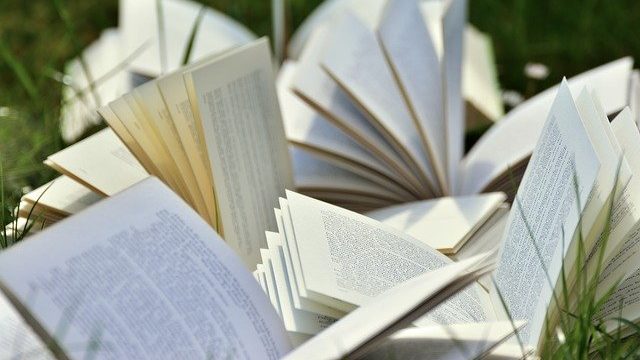誰かとの繋がりがあるってことはそれだけで生きる希望となる。
一緒にいなくても、遠く離れていても、それって本当だと改めて思わされます。
今回読んだのは、東野圭吾さんの『希望の糸』です!
『希望の糸』は、大人気シリーズの一つである〈加賀恭一郎〉シリーズの第11作品目にあたります。
前作の『祈りの幕が下りるとき』で、
「シリーズ完結か!」
と思っていたので、次が出たことがとてもうれしい。
今回は、加賀よりも、いとこである松宮脩平を中心に物語が進んでいきます。
それでも光る、加賀の有能さ。読みごたえ抜群です。
ここでは、『希望の糸』のあらすじや感想を紹介していきます。
Contents
『希望の糸』のあらすじ
閑静な住宅地で小さなカフェを営む店主の女性が殺害される。
すぐに捜査本部が立ち上げられ、松宮脩平は捜査に乗り出す。
調べていくうちに、被害者である弥生には、最近、仲の良い汐見という男性がいたことがわかる。
汐見は、女性の客が多い中、数か月前から店に通うようになっていた。
一方で、弥生は、殺される少し前に、元夫と連絡を取っていることもわかった。
容疑者として浮かんできた二人であったが、松宮たちの捜査は難航していく。
そうして事件の捜査をしていく中で、一人の人物が重要なカギを握ることがわかっていく。
巡り会いが人生を豊かにする
久しぶりの加賀恭一郎シリーズ。
さすがのおもしろさでした。
いろいろとテーマ性もありましたが、気に入ったのは巡り会いという考え方。
人生ってのはいろんな人との巡り会いでできている。
友人にしたって、恋人にしたって、生まれてくる赤ちゃんにしたって。
『希望の糸』の中では、不妊治療の話も出てくるんですよね。
子どもが欲しくて、頑張ってみたけれど産むことができなかった人。
不妊治療の末に、最後の最後で、子どもを授かることができた人。
ただ、子どもができなかったから不幸ってわけではない。
それも一つの形であり、いまある、これから来るであろう巡り会いの一つ一つを大切にしていこうって。
巡り会いって言葉で思うのは、新しい人と出会うと同時に、いくらかの人とはお別れしていくってことです。
中学、高校、大学、社会人と経てきて、いろんな出会いがあって、楽しいこともうれしいこともありましたが、そのときの仲間っていまでも大事に感じます。
でも、いつまでも一緒にいるわけじゃないのは当たり前。
今はそれぞれ家庭を持っているから、ほとんど会うことも連絡することもなくなってきましたが、そのころに出会った人たちによって、いまの自分はあるんだろうなって感じます。
巡り会いの中で影響を受けながら、また新しい巡り会いへと入っていくんだろうなと。
繋がっていること、それが大切
繋がりって言葉も、『希望の糸』では大きな言葉して感じられます。
昔から個人的にも、この「繋がり」って言葉は好きなんですよね。
そういえば、大学時代の論文でも、こんなテーマで書いたような記憶が。
さて、上記したように、人生ではいろんな人と出会って別れてを繰り返していきます。
このときに築いた繋がりって、離れて、会うことがなくなっても、どこかで繋がっているものなんだろうなって思います。
「あの人との繋がりがあるから、頑張れる」
そういう出会いや経験ってあると思うんですよ。
私自身も、仕事にしてもなんにしても、なんだかんだそうした繋がりに救われているところがあります。
誰も誰かの代わりにはなれない
『希望の糸』でかなり重要な役割を持つのが汐見萌香です。
汐見夫妻の娘と生まれた萌香だったけど、実は萌香の兄と姉がいました。
でも、二人はプロローグで描かれる震災で亡くなってしまう。
失意の汐見夫妻は、自分たちが立ち直るために子どもをもう一度作ろうと話し合い、生まれたのが萌香でした。
だから汐見夫妻も、萌香のことをとてもかわいがったし、大切に育ててきました。
それはもう心配のし過ぎで過保護だなって思うくらいに。
そして、ことあるごとに、二人の姉と兄の話をします。
「二人の分まで幸せになってほしい」と。
親の立場からするとすごくわかる気持ちです。
でも、それを託される側としてはとても重たい。
「私は誰かの代わりじゃない!」
って言いたくなる気持ちもわかります。
人を誰かの代わりになんてなれないし、しようとしてはいけないのだと思います。
誰だって、自分のことをちゃんと見て欲しいしわかってほしい。
誰かの代替としての存在では、一時的な満足はあっても、幸せかって言われると疑問符が浮かんできます。
血の繋がりがすべてではないが
血の繋がりって大事でもあり、そうでもなかったりする。
いやね、大事だとは思うんですよ。
自分の子どもだから、世の中にいるほかの子よりも愛おしいと思うし、大切にするんだと思う。
だからある意味、それだけでその人って特別なんですよね。
そこは間違いない。
じゃあ、血縁関係がなかったら駄目なのかというと、そういうわけでもない。
血の繋がりがなくても、親子で育んできた時間も、愛情も尊いものだから。
よく家族をテーマにした小説だと、血の繋がりを意識させる作品ってけっこうあるんですよね。
いや、意味合いとしては、血の繋がりがなくても、そこには確かな絆がある的なほうがおおいでしょうか。
瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』なんかも、血の繋がりがなくたって、しっかりとした親子が登場しますよね。
すごく好きな作品の一つです。
東野圭吾さんの作品だと、この〈加賀恭一郎〉シリーズ全体で、家族を扱うものが多い。
『赤い指』や『麒麟の翼』なんてまさにそうだし、家族ってなんなんだろうって考えさせられるものがたくさんあります。
『希望の糸』もその一つで、家族って血の繋がりだけじゃない、でも、血の繋がりがあるということだけでも、とても意味があるということを感じさせてくれます。
おわりに
東野圭吾さんの作品はやはりさすがとしか言いようがない。
プロローグを見ただけでは、いったいどんな話になるのかさっぱりわからない。
でも、そのプロローグがしっかりと重要な位置を占めているんですね。
〈加賀恭一郎〉シリーズはこれで11作目。
全部読むのは大変!って感じるかもですが、これが意外とするっと読めてしまいます。
それだけ一冊一冊がおもしろいからですね。