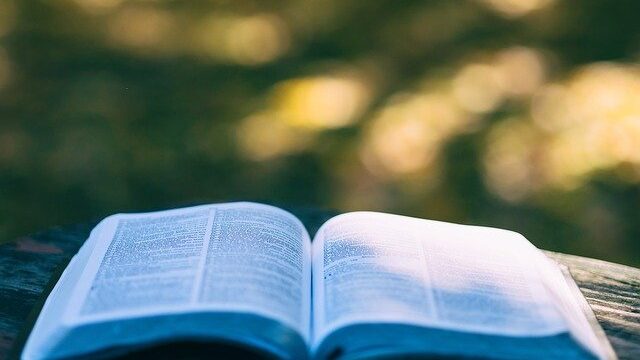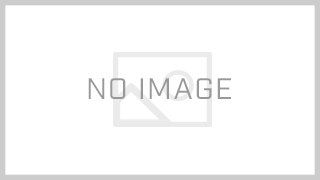私の大好きな作家の一人である芦沢央さん。
長編も濃厚で好きなんですが短編が特に秀逸。
『嘘と隣人』もまた、連作短編という形ですが、一作一作に引き込まれてしまいます。
Contents
■あらすじ
『嘘と隣人』は、定年退職した元刑事、平良正太郎 を主人公とする連作短編集。
かつて刑事として数々の事件を扱ってきた彼は、今は警察を辞め、平穏な余生を送っていた。
しかし、身近な人々との関係、あるいは過去にかかわった場所や事件をきっかけに、ふたたび“事件”は彼の前に姿を現す。
すでに警察を辞めている正太郎には捜査権がない。そんな中でも、自らの洞察力と過去の経験で事件を紐解いていく、紐解いてしまう。
事件の真相ともに、そこに隠された隣人の”嘘”も暴かれてしまう。
そこには他者の中に潜む悪意が込められていた。
“嘘”が生み出す歪み
『嘘と隣人』では、タイトルの通り、隣人と彼らのついた”嘘”がキーワードになっている。
たった一つの嘘によって、大きな事件に発展しているものもあれば、その嘘さえなければ生じなかった事件もある。
ただ、ついた嘘は、ごくありふれたもののようにも思われる。
現実にもどこかで誰かがついているような嘘。
しかし、それによって、その場に生まれた歪みが大きな被害を生む。
収録されているエピソードは、『かくれんぼ』『アイランドキッチン』『祭り』『最善』『嘘と隣人』といった五編で、どの短編においても“嘘”あるいは“見えない事情”が鍵になっている。
例えば、「かくれんぼ」では、離婚調停中の母親をめぐる事件。
ストーカーと化した夫から逃げ隠れる母子のもとに、夫が居場所を突き止めて現れるものだ。
居場所は知られていなかったはずなのになぜ夫に居場所が分かってしまったのか。
「アイランドキッチン」では、とあるマンションでの転落死が事件として上がる。
その転落死は、自殺だったのか他殺だったのか。
現場の状況や証言から警察は判断を下すが、とある嘘が発覚することで、その背後の“もう一つの真相”が浮かび上がる。
引越し業者と技能実習生をめぐる事件、駅のホームで起きた乳児の転落事故と痴漢冤罪という絡み合った事件と、どれも実際に現実に起きそうな事件ではある。
それが余計に一つ一つの話を身近に感じさせリアリティを生み出している。
● “嘘”の多様性とその影響
嘘をついたことがないという人はいったい世の中にどれくらいいるだろうか。
幼少期には親から嘘はついてはいけない、と言われながらも、ちょっとしたきっかけで嘘をついてしまうという経験は誰しもが持つものだ。
本作で描かれる“嘘”は、多様だ。
被害を避けるための嘘、人を守るための嘘、体裁を保つための嘘。
時には無意識に、思い込みや恐怖がつくった嘘。
実際にどれを見てみても、嘘としてはよくありそうなものではある。
人が嘘をつくとき、そこにはその人なりの理由や理屈がある。
それは自分を守るためかもしれない。
それは誰かへの嫉妬や悪意かもしれない。
それは自分の利益のためかもしれない。
『嘘と隣人』で起きた嘘による影響は甚大なものだ。
嘘をつくとき、嘘をついた人にそこまでの意図があったとは思えない。
一方で嘘によって被害を受ける相手への視点は欠如している。
自分のために誰かが犠牲になっても構わない、利己的な人間の本性が暴き立てられている。
「隣人」という身近な他者の中にこそ“嘘”と“悪意”が潜むという恐怖。
それは自分たちの側でも起こり得ることだと感じさせる作品だ。
● 「解決」することが良いわけではない
『嘘と隣人』では、派手などんでん返しや見事な事件の解決というものはない。
しかし、それだけに読後に心に重たいものが残るのではないだろうか。
事件の真相が明らかになったとき、多くの場合、その先に残るのは後悔、絶望、無力感といった負の感情。
もしくは自分だったらどうしただろうか、その場にいたときに正しく行動できただろうかという問いが投げかけられる。
”嘘”を見抜き、事件の真相を知る。
その言葉だけを聞くと事件が解決して良かったと感じるかもしれない。
しかし、”嘘”を知ってしまったからこそ、その人との人間関係にはこれまでと同じようには接することができない亀裂が生まれてしまうこともある。
『かくれんぼ』にしても、『最善』にしても、当事者であったり、その近くにいる人間だった場合、その人物への見方は大きく変わるはずだ。
知らなければよかった”嘘”というのもあるということも感じてしまう。

posted with ヨメレバ
芦沢 央 文藝春秋 2025年04月23日頃