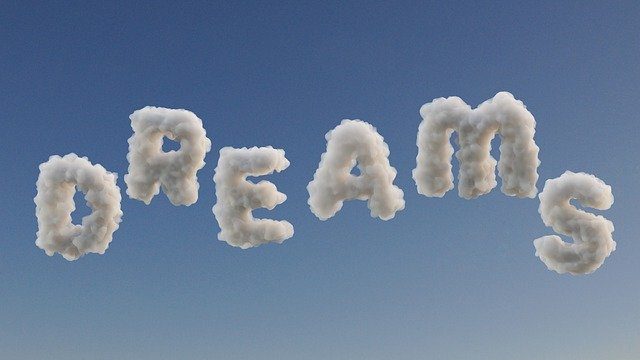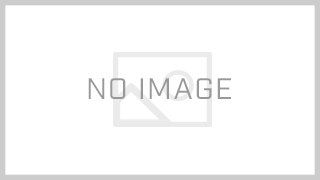汽水域という言葉を聞いたことがあるだろうか。
汽水とは、海水と淡水が混在した状態の液体のことをいう。
海に近い河川や沿海などで汽水が占める区域が汽水域だ。
海に近いほど海水が多く含まれ、遠ざかるほど淡水の割合が増える。
その割合は一定ではなく、そのときどきの潮の満ち引きなどによっても変化する。
白黒とはっきりしたものではなく、どちらも併せ持った状態で、どちらに変わるかは状況次第。
それは人の心にも似たものだと言える。
人の感情は移ろいやすいものだ。
幸せだと感じると同時にどこかに不満を抱えていたり、不幸だと嘆く中にも喜びが勝る瞬間がある。
人間の善の部分と悪の部分がときとして逆転してしまうことだってあるだろう。
岩井圭也さんの『汽水域』はそんな人間の感情を見事に表現している。
本書は、とある男性による歩行者天国での無差別殺傷事件から始まる。
三人が亡くなり、四人がけがを負ったという重大事件で、犯人の深瀬はその動機を、
「死刑になりたかった」
からだと語る。
メディアが大々的に事件を報道する中で、フリージャーナリストの安田は出版社からの依頼でこの事件を追うことになる。
この安田という男がまたけっこうなダメな男で、結婚して子供も生まれたのに家庭を顧みずに仕事にのめり込み、あっという間に離婚。
月に一回の息子(小学一年生)との面会では、釣り堀に行き、ほとんど会話がないまま時間をつぶす。
息子も釣りよりもゲーム実況の動画を見ているという状況。
事件の依頼を受けると、面会中の息子を車に乗せて事件現場に向かい、車から出るなと言い残して三時間近くほったらかし。
元妻からも怒られ、それでも自分本位の生き方を変えられずにいる。
そんな安田だが、運なのか実力なのか、最初に書いた殺傷事件の記事が反響を呼び、この事件を週刊誌での連載するために、深瀬とかかわりのある人物にインタビューしていくことになる。
そしていつしか、深瀬がどうしてこんな事件を起こしてしまったのか、その真相を追い求めるようになっていく。
事件には被害者と加害者の側面がある。
もちろん、事件を起こした人間が加害者であるのだが、その加害者にしたって、何かの被害者であることがある。
なぜ犯人が事件を起こしたのか、その裏側には何があるのか。
それを知ることも事件を教訓として生きていく社会にとっては必要なことなのだと思う。
一方で、社会を揺るがすような大きな事件であっても、それをただのコンテンツとして消費していく動きがあることも否めない。
『汽水域』の中では、深瀬を擁護するようにも読める記事を書いた安田に批判が殺到する。
批判した人には、そこにどれだけの信念や理念があったのだろうか。
おそらくただ思うままにコメントを送ったのだろうと思う。
こうした動きというのは実際の社会にだってあることだ。
当事者ではない事件に対しては好きなことが言える。
大きな事件があっても、けしからんということは簡単だ。
ただ、そこから一歩踏み込んで、考えてみて、自分自身に当てはめてみることはそうできることではない。
また、『汽水域』は、人の危うさやつながりの重大性を示唆してくれている。
出会った人やつながりで人はどのようにも変わるもの。
生きていると苦しいことも嫌なことも誰にだってあるものだ。
仕事一つにおいたって、一度くらい辞めてしまいたいと思う人が多いのではないだろうか。
そんなときにそれでも頑張れるのはなぜか。
それは家族の存在だったり、職場の同僚に恵まれていたり、困ったときに相談に乗ってくれる友人の存在かもしれない。
そうしたつながりが、どこかに転げ落ちそうなときでも踏み止まらせてくれる。
逆に言えば、なにもつながりがなくなってしまえば、極端な場所に流されていってしまう可能性を含んでいる。
深瀬と安田の違いはなにか。
そこにはたとえ細くても引きとどめてくれるだけのつながりがあったからだと言える。
今一度、自分がいま、健全に生きていられる中で、いったいどれだけのつながりがあるのかと考えてみたい。
大きく自分自身に影響を与えているものがある。
そういえばこんなつながりもあるな、といった程度の細いものだって考えてみると意外とたくさんある。
細い線であっても重なって束ねられていくと強靭なものになっているように感じられる。
海水と淡水が混ざり合ったような意識の中で、真っ当に生きていけていることと、そこにとどめてくれているたくさんのつながりに感謝をしたい。