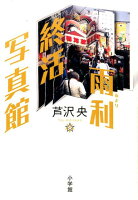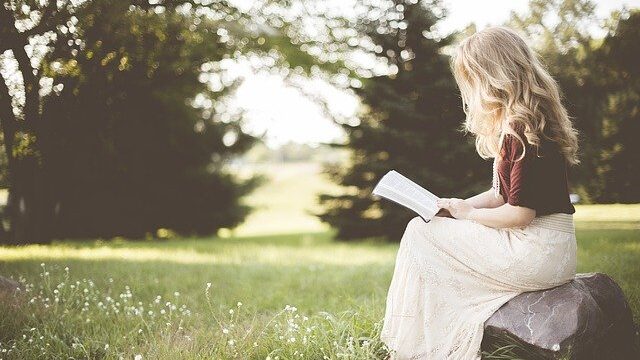終活というと、
「自分にはまだ早いかな」
なんて思っていましたが、そうでもないかもしれない。
こういう形の終活もあるのだと一つ感じさせられる作品でした。
今回読んだのは、芦沢央さんの、『雨利終活写真館』です!
芦沢央さんの第6冊目にあたる作品で、連作短編集となります。
連作短編っていいですよね。
芦沢央さんって、長編ももちろんおもしろいんですけど、私は芦沢央さんの短編が大好きで。
それが連作短編という形でがっつりつながっている。
それだけでもう先が気になって仕方がなかったです。
ここでは、『雨利終活写真館』のあらすじや感想を紹介していきます。
Contents
『雨利終活写真館』のあらすじ
巣鴨に店を構える雨利終活写真館。
ここは、遺影専門の写真館であった。
お金にうるさい店長、並外れて不愛想なカメラマン、関西に住んだこともないのに、少し変な大阪弁を使うアシスタント。
個性的なメンバーで運営されたこの店に、黒子ハナは訪れた。
「一つ目の遺言状」では、祖母の残した奇妙な遺言状の謎を黒子ハナが追う。
祖母が遺影を取った写真館へ、遺言状のヒントになるものがないかと訪れた。
「十二年目の家族写真」では、息子が小さい頃に、マンションから転落して死亡した母親の死をめぐる、息子と父親の葛藤を描く。
「三つ目の遺品」では、雨利写真館に残る1枚の妊婦写真に焦点が当てられる。
この遺影は誰のためのものだったのか。
「二枚目の遺影」では、末期癌を患う男性が、別々の女生と、それぞれ遺影写真を写真館に依頼する。
「誤解」を解き明かす物語
『雨利終活写真館』では、四つの物語が描かれています。
いずれにも共通するのは、「誤解」があるということです。
この「誤解」の生み方がとても自然。
話だけ聞いていると、そう考えてもおかしくない状況ばかりが出てきます。
読み始めは、
「これもけっこう悲しい話になるのかな」
と思わせるところもあります。
芦沢央さんのほかの作品って暗い雰囲気のが多いんですよね。
『罪の余白』にしても、『いつかの人質』にしても。
『雨利終活写真館』でもそうかなと思っていたらこれがまた違うんです。
そこにある誤解によって、どこかすっきりしない、もやもやとした気持ちを抱えている登場人物。
でも、ストーリーが進んでいき、誤解が解き明かされていく先には、また違った景色が用意されています。
こういう最後は心がほっとする話ってすごく好きです。
終活を考える
さて、終活って近年ではよく耳にするようになりました。
エンディングノートを作ろうとか、残された人がもめてしまわないようにとか。
私は今年で38歳なので、正直まだ自分には早いと思っていましたが、でも人間どうなるかなんてわからないですもんね。
こういう、残された人たちの物語を読むと、
「私も生きているうちになにかしたほうがいいのでは」
という気持ちにさせられます。
幸い、いまのところ健康問題にはなにも異常はないのですが。
でも、万が一、自分がいなくなったとき、妻と娘はたぶんすぐにはなにも手につかないだろうなと。
最低でも、もしそうなってしまったときに、この手順で動くようにといったものだけでも残しておかねばと。
それが残される人の幸せを考える上では必要なことだと感じました。
おわりに
とても読みやすい小説で、きっとこれって映像化もしやすいのではないかなーと感じます。
芦沢央さんって、今の時点ではあまり小説が映像化されていないんですよね。
『罪の余白』はされていたかな。
それ以外は記憶になし。
『雨利終活写真館』は、登場人物が個性的だし、内容的にも、けっこう映画になってもおもしろく描ける気がするんですよね。
人気のある作家さんの一人なので、これからどれか映像化されたら、一気にほかの作品もなりそうですね。
すごく楽しみです。
芦沢央さんも残すはあと三冊!