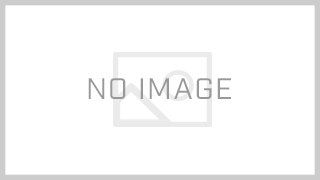柚月裕子といえば、『孤狼の血』、『月下のサクラ』といった警察小説や、『教誨』のような犯罪をテーマにした作品を多数出している作家だ。
今回紹介する『ミカエルの鼓動』は医療の世界に踏み込んだ作品になる。
医療ジャンルは、専門知識の壁や職場独自の倫理観などの複雑さゆえに、作家にとっても読者にとっても難度が高い領域と言える。
前半は医療現場ならではの人間関係などの説明に文量を割かれているが、それが後半の展開にいきてくる。
専門性の高い内容は、とっつきにくいと考える人もいるが、その“専門性の高さ”を障壁とせず、「命に向き合う人間の揺らぎ」を物語の中心に据えることで、むしろ医療小説ならではの奥深さを感じさせる構造になっている。
主人公・西條泰己は大学病院に所属する心臓外科医であり、手術支援ロボット「ミカエル」の第一人者として最先端医療の実現を目指す人物だ。
彼を軸として、医療技術の進歩、個々の医師の信念、病院組織の論理、患者と家族の思いといった多層的テーマが絡み合い、濃密な人間ドラマが展開されていく。
本書を読み終えたとき、私は「これは医療小説である前に、人間の正義を描いた作品だ」と強く感じた。
Contents
■あらすじ──交錯する理想と現実、そして組織の影
物語の中心にいるのは、心臓外科医・西條泰己。
ロボット支援下手術の第一人者として内外から名前を知られている人物である。
彼は手術支援ロボット「ミカエル」に大きな可能性を見出していた。
時間のかかる準備時間を短縮し、従来よりも短時間で手術を終えることで患者の負担を減らすことができる。
専門医のいない遠隔地でも、ミカエルがあれば遠くにいながら手術ができ、質の高い医療が広範囲に平等に提供できる。
西條はそのような未来を本気で目指していた。
単に技術革新への憧れや功名心ではない。そこには、救えなかった命への悔恨や、医療格差の是正への強い思いがある。
対照的な存在として現れるのが、ドイツ留学から帰国したばかりの天才外科医・真木一義だ。真木はロボットを用いず、従来の開胸手術を高度な技術で成功させる。
どちらも「患者を救いたい」という思いに基づくものだが、二人の価値観は根本から異なっている。
彼らの対立が表面化するのは、難病を抱える少年・白石航の治療方針を巡ってである。
ミカエルを使った人工弁をつける手術を推す西條と、人の手により人工弁を必要としない開胸手術を主張する真木。
真木の方針に一定の理解もありながらも、西條はミカエルでの手術が成功すれば、ロボット支援下手術を広めることができる、と引くことができなかった。
さらに物語を複雑にしているのは、病院内部の政治である。ロボット導入を巡るメーカーとの利害関係、大学病院特有の派閥争い、過去の医療事故との関係。
西條や真木が純粋に患者を救おうとするほど、組織の暗部や圧力の存在が浮き彫りになっていく。
そして、作品に深い陰影を落とすのが、西條を尊敬していた若手医師の突然の自殺だ。この出来事は、医療現場の過酷さ、理想と現実の乖離、医師たちの心理的負担の象徴として描かれ、物語全体に強い衝撃を与える。
手術ロボット「ミカエル」をめぐる疑惑が深まる中、真相はどこにあるのか。何が正しい医療なのか。命と信念をめぐる問いが、物語をクライマックスへと導いていく。
ロボット医療と人間の技術、その“どちらも正しい”世界
本作の最も興味深い点は、「医療に絶対の正義はない」という点を徹底的に描いているところだ。
ロボット手術は、患者への負担を減らすことができ、医師の技術差を軽減し、遠隔医療を可能にするという革新性を持つ。
西條の信念は、医療の未来を真剣に考える者として自然である。
しかし一方で、ロボットでは絶対に代替できない“人の手の感覚”というものが確かに存在する。真木の技術は、まさに人間が長年積み上げてきた経験そのものであり、難手術の成功率に影響する。
どちらも患者を助けたいという点では同じであるが、それぞれのこれまでの体験がその信念へと繋がっており、互いに譲ることができない。
読んでいるうちに気づくのは、「どちらの医療が正しいか」という選択ではなく、「医療そのものに複数の正義がある」という事実だ。
医師もまた“揺らぐ人間”であるというリアリティ
西條も真木も、決して完全無欠のヒーローではない。
西條は理想主義的であるがゆえに、時に視野が狭くなり、周囲を巻き込んでしまう危うさを持つ。真木は技術に絶対の自信を持つが、そのプライドゆえの傲慢さが彼の弱点でもある。
もし、しがらみもプライドも何もない状態で二人が手を取り合えば、理想的な医療現場が生まれるのかもしれない。
しかし、西條にもロボット支援下の第一人者で追い求める理想もある。
真木にも、自身の過去が覆いかぶさり、そこから生まれた信念を譲ることは難しい。
本作の中には、若手医師の自殺に関連するエピソードである。
医師たちは、しばしば「強くあること」「完璧であること」を求められる。しかし実際には、命の現場で揺らがない医師などいない。
本当にこれが最善だったのか。
自分の選択は間違っていたのか。
人と触れる以上、完璧な正解などなく、一つ一つ模索しながら手探りになる。
その中では自分なりの答えを出していくが、その過程は簡単なものではない。
本作は、その“弱さ”や“恐れ”をも丁寧に描き、人間としてのリアリティを与えている。
単なる医療ドラマではなく “人間ドラマ”として読むことができるのは、柚月裕子の筆力の強さである。
病院組織と利害の描き方が圧倒的にリアル
大学病院が舞台というだけで、すでに独特の空気がある。権威、派閥、予算、研究実績、政治力。これらが複雑に絡み合い、医師たちの純粋な信念を時に押しつぶす。
ロボット導入に絡むメーカーとの関係性、広報や報道との駆け引き、患者家族への説明の難しさ。これらが非常に現実的に描かれており、読み手は「医療は医療だけで成り立っているわけではない」という現実を突きつけられる。
医療の現場は清廉潔白な理想だけでは回らない。制度、政治、社会、経済、すべてが命の現場に影響する――そのことを、本作は強く示している。
“問い”を残す読後感こそが作品の価値
物語を読み終えたあと、私は明確な結論を持つことができなかった。
西條の理想は尊く、真木の矜持もまた揺るぎない。病院組織の論理すら、単純な悪として切り捨てることはできない。
つまり本作の魅力は、“答えを提示しないこと”にある。
命を救うとはどういうことか。技術革新は何を可能にし、何を奪うのか。医師はどこまで患者のために尽くせるのか。組織はどこまで個人の正義を許容すべきか。
それらの問いは、読後もずっと胸の中で鳴り続ける。
深い余韻の残る、現代医療を映す鏡のような一冊
『ミカエルの鼓動』は、手術ロボットを題材にした技術的な興味、医師たちの信念のぶつかり合いというドラマ性、そして病院組織の暗部を描く社会派要素が見事に融合した作品である。
医療小説が好きな人だけでなく、社会問題に興味がある人、人間ドラマが好きな人にもぜひ薦めたい。
テーマは重く、決して読みやすい明るい作品ではない。だが、ページを閉じたあとの余韻は深く、読者の心に静かに残る。「命とは何か」という問いの重さを真正面から描いた作品だからこそ、読後にしばらく言葉を失うような読書体験となる。
読み終えた後、あなたはどの医師に共感するだろうか。どの正義を選ぶだろうか。
その答えは、読者一人ひとりの中にあるのだと思う。